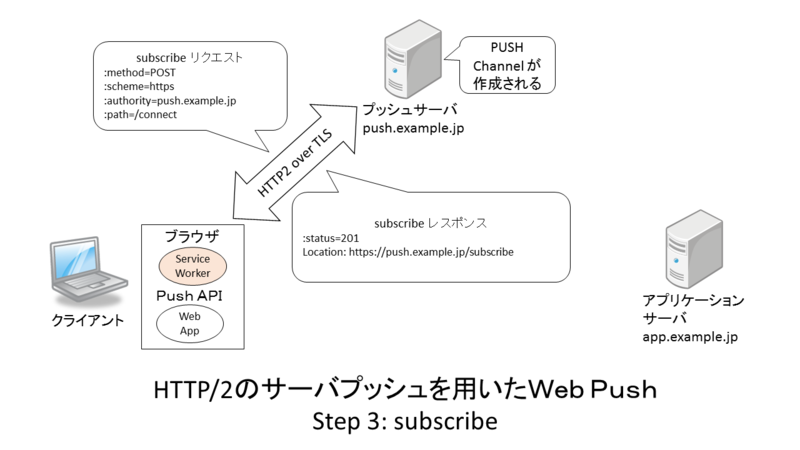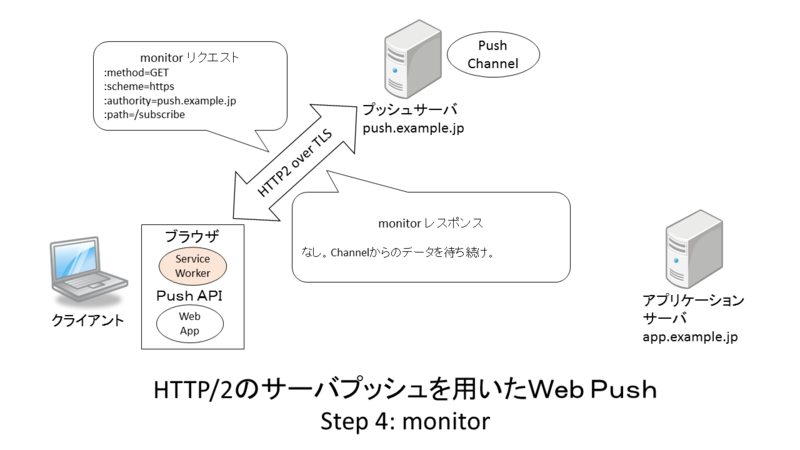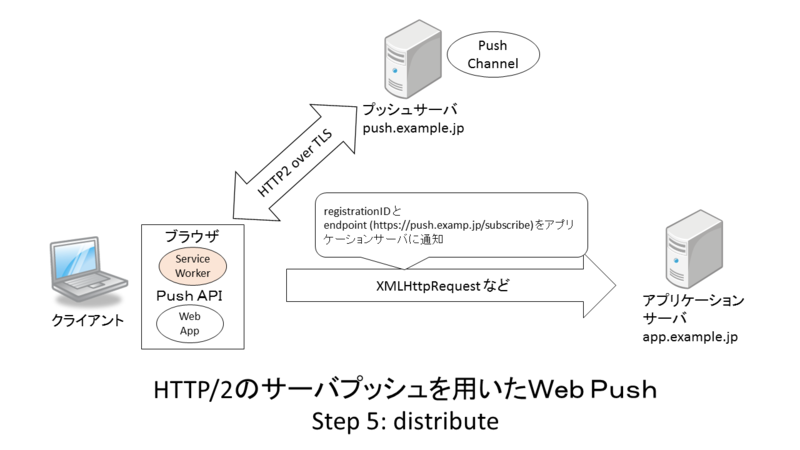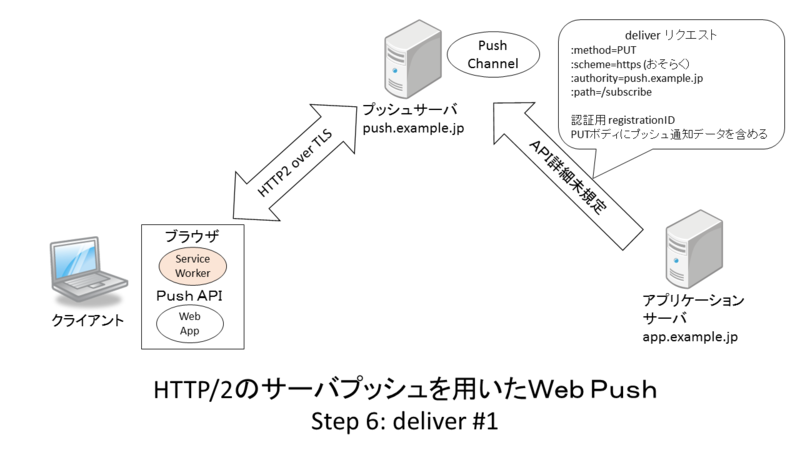1. 祝 io.js-v1.0.0/1.0.1 のリリース
NodeやJSの情報にアンテナを張っている人なら知っているとは思いますが、昨日無事「io.js」がリリースされました。
リリース直前のバグ修正の追い込みやライブラリアップデートのごたごたは、かつてのNodeのリリースそのままでした。
今日のリリースを予言していたわけではないですが、実は昨年の8月初旬に、
これがまさに現実になってしまったなぁ、と驚きと共に感慨深いものがあります。
Nodeの方は、今Julienが頑張ってチケットをクローズしており、近日中に Node-v0.11.15がリリースされる予定です。問題なければNode-v0.11.15のリリース2週間後にNode-v0.12 になるでしょう。
io.jsができた細かい経緯については、古川さんの「io.jsについて知っていること」が詳しいです。ただ長年Nodeコアの開発を見てきたこともあり、自分の目線で今回のio.jsリリースまでを振り返りたいと思います。
ただし今回のio.jsのフォーク騒動を当事者ではなく完全外から見ていた人なので、完全に自分の主観で書いています。当事者間でないとわからない部分も多々ありますので、その点ご留意してお読みください。
2. V8更新から見たio.jsフォークの経緯
なぜ8月頭にフォーク話を書いてしまったのか?
当初Node-v0.12で予定されていた機能の大部分は昨年4月頃に既に実装されていたのに遅々としてリリースされない状況を見てそう感じました。
今回改めてNodeでのV8の扱いを軸に時系列で書いていくとio.js がフォークに至った経緯などがよく見えてきます。

象徴的な部分、上表で注釈1,2で書いた部分は以下に書かれている項目です。
- (*1) https://github.com/joyent/node/commit/67e078094b53861a5aa7e9354e33487d0bd4f73b#commitcomment-5875896
- (*2) https://github.com/iojs/io.js/blob/v1.x/doc/tc-meetings/2014-10-15.md (議事録下部V8の部分)
TJFは、Node on the Roadイベントで各地を回り、これまでのNodeのバージョンアップに伴うユーザの大変さを理解したと綴っています(Notes from the Road)。このような声を受けて、NodeのV8の対応(特にES6対応)には当初保守的に考えるようになったのでしょう。
対して技術志向を持つメンバーには、このような保守的な考えはなかなか受け入れにくいものだったと想像できます。進化し続けるV8にNodeが追従していくのは、バグフィックス等の安定性や性能の向上に寄与し、さらにブラウザでデフォルトで利用される予定のES6の新機能がタイムリーに利用できるという考えではなかったでしょうか。
V8の扱いは一つの要因で、他にもいろいろ理由はあると思いますが、こういった方向性の違いからio.jsが生まれたのではないかと思っています。
3. io.js-v1.0.xとNode-v0.12の相違
io.jsは v1.0.x なのに、なんでベータ扱いやねんと不思議に思われる方もいるでしょう。semverでは、 Public APIを規定した1.0.0からバージョンが始まります。今後 iojs-v1.0.x はパッチレベルの修正、iojs-v1.1.x は後方互換を保った変更、iojs-v2.x.y は後方互換を止めた変更といった形で開発が進むものと思われます。
3.1 iojs-v1.0.1 が Node-v0.12 と同じところ
io.js-v1.0.0 は、Node-v0.12 の Public APIと完全互換でリリースされ、 semver に従ってNode-v0.12との互換性が保たれる方針です。ただ現時点ではio.js の方が開発スピードが格段に速いため、バグフィックスなどによる挙動の違いなどが現れる可能性があります。
また io.js は、Node-v0.10系とは互換でないので気を付けてください。0.10系で既存のNodeアプリを使われている方は、 Node-v0.12(Node-v0.11.15)でも動作するか確認が必要です。
io.js のCHANGELOGは、Node-v0.10.35からの変更点が記載されています。CHANGELOGで書かれている部分の半分ぐらいは下記スライドで解説していますので、参考にしてください。
3.2 iojs-v1.0.1 が Node-v0.12 と異なるところ
現状で表面的に異なる部分は、
- V8: iojs-v1.0.1 は V8-3.31 ベース(Node-v0.12は V8-3.28)。外部的にはデフォルトで使えるES6の機能が異なります。
- event モジュール: iojs に getMaxListenrs() メソッドが追加
- domain モジュール: domain.run() に引数が使える。ドキュメントに廃止予定の告知
- v8 モジュール: v8のヒープ情報や動的フラグ設定などの機能を追加(実験的API)
などです。
当初io.jsでは、fs.existや.fs.existSync のAPIを廃止していましたが、 Node-v0.12とのAPIとの互換性保持のためリリース直前に復活しました(でも今後廃止予定です)。 他にもマニュアル、バグフィックス、最適化、ビルド対応など細かい部分が io.js で変更されています。
4. で今後どうなる?
うーん、わかりません。
現状では、Joyent Node側は、リソースを一緒にして協力したい。 io.js側は Open Governanceモデルで迅速に開発を進めて、将来的に io.js から Node (1.0)へマージして欲しいという感じです。今後コミュニティがうまく両者が両立して使い分けられるのかにかかっているでしょう。良い形で両者が協力できるよう落ち着くことを祈るばかりです。
いずれにせよ、今回の io.js-v1.0.0のリリースと近日のNode-v0.12のリリースで両者の開発が短期間で大きく前進したのは確かです。個人的には、今年半ばに仕様化完了が予定されているES6の機能が充実していくことによって、io.jsやブラウザのJavaScriptの世界がどのように変わるのか非常に楽しみです。